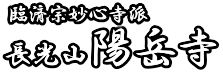世界中の人々が、新型コロナウィルス感染症の猛威にふりまわされています。皆さまの身体ご自愛祈念申し上げます。
感染症対策では、集まってはいけない、と言われます。しかし集団は楽しく、横ならびの安心感を得られます。面倒なところもあるけれど。
しかし、ひとりもつらい。だれかと話したい、会いたい。ひとりは楽なところもあるけれど。
集まっても問題、ひとりも問題です。
過度な関わりも孤独も遠慮したい。しかし、ひとと関わって、ものと関わって生きていく私たちには、ここをどうするか悩むものです。コロナ禍は特に、と言ってもいいかもしれません。
社会にかかわりすぎると、ひっぱられてしまう。ひとりでいすぎると、しゃべりかたを忘れてしまいそうになる。こればかりは避けようがない事実です。永遠に思慮すると書いて遠慮ですが、つながりのなかに生きている人類だからこそ、永遠に考えられてきた問題なのでしょう。
2500年前のお釈迦さまも考えました。「社会への同調」「ひとりでいること」に、ふりまわされない。取り込まれないことが大切なのかもしれない。それが本当に自由でいることだと。
では、わたしたちは、日々の生活のなかどうすればいいのでしょうか。とりこまれていないか?と俯瞰する機会をもうけて、自分の道を歩むしかない。
今回は、仏教の「中道」をヒントにしたいと思います。
◆「中道」は、ほどほど・まんなか、ではない
「中道」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。
この言葉が出てくるのは、いわゆる初転法輪(しょてんぼうりん)のときです。
仏教のはじまりとなった人間、お釈迦さまがお悟りを得て、むかしの修行仲間に会いに行きます。そして自身のお悟りの内容について、はじめて他人に話すのです。これを初転法輪といいます。その語る内容に「中道」があります。
◆中道とは:初転法輪にて
かつての仲間に、語った内容の「中道」とはまとめると…
幸せに暮らす道を歩みたいならば、ふたつの偏った道を避けたい。ひとつは欲に負ける生活、もうひとつはいたずらに自分の心身を責め苛む生活。この見方、あの見方とどのような見方の後も追わない生活を「中道」という。とらわれるとき、迷いの生活が始まる。迷いを離れ、さとりをも離れることだ。
(長いですが、日本語訳原文として『仏教聖典〜鹿野苑篇 第29節 中道』、友松円諦 訳も記します。)
汝ら、これらふたつの極端は修行者たるものの避くべきところなり、なにをかふたつの極端となす、ひとつにはもろもろの欲の上に楽しみ耽ること、これはいやしく、凡夫のなすわざにして、聖者のなすところにはあらず。〜。ふたつには自己を苦しむることにのみつとむること、これただ苦痛にして、聖者のなすわざにあらず。〜。汝ら、如来はこれらふたつの極端によらずして、中道をさとりたるなり。〜。この世間は多く有と無とのふたつの極端をよりどころとせり。〜。きわめていやしき欲楽のわざを求めて、凡夫のおこないをなすなかれ。またみずからかいもなき苦行を求むることなかれ。このふたつの極端を離れんこそすなわち中道なれ。この世にて、功徳と罪悪とのふたつのまよいを伏せ、これを去り、貪をはなれ、こころ清浄なるもの、かかる人をわれは婆羅門といわん。
◆中道を知ると
「中道」について知ると、ものごとを天秤にかけてしまう分別心をひとは持ってしまうこと。そこからの脱却が大切だと知ることができます。
お釈迦さまという人間が、ご自身の人生経験から出た答えです。
社会のなかに生きて、他者とかかわり、されど社会に取り込まれない。欲とともに生きて、慎みとともに生きて、されどわがままや虚無感にも取り込まれない姿勢を知ることができる、とも思うのです。
ちなみに中道とは、「両極端ではないこと」「真ん中をとること」「ほどほどがいい」「曖昧である」という意味では使えません。儒教の中庸も同様です。
◆どうしても取り込まれてしまう
想像ですが、「中道」の背景を考えてみます。
お釈迦さまは小国の王子として生まれます。お生まれになったとき、世界を制覇する王になるとも、素晴らしい宗教者になるとも御告げがあります。そこで城の者たちはお釈迦さまが城から離れぬように、享楽をあたえます。すばらしい建物や宝物、しかしそんななかに浸りながらも、家を離れる因縁を得ます。
出家後、さまざまな修行者に出会い、道を求め、仲間を得ます。出家者による当時の現地の苦行に浸り、苦行をしきって死を覚悟します。しかしそこでひとり苦行をやめます。そしてお悟りを得た。難行苦行という誘惑を断ちました。
これが正しい自覚の道「中道」にいたるお釈迦さまの人生の歩みです。お釈迦さまはさまざまな享楽を得て、離れた。さまざまな苦行を経て、離れた。与えられた享楽を当たり前に暮らしたり、当時現地の“ザ・修行”をしたり。とらわれてしまうものの、しかし彼は離れた。
きっかけはさまざまでも、ものごとを天秤にかけてしまう分別心をひとは持ってしまう、持たされてしまう。でも、どうにかできる。そんなことを、生き様から教えてくれています。
この説話を聞くと、享楽と苦行を経験して、これらは両極端だな…と認識したからお釈迦さまは「中道」を得たように思いそうになります。しかし、そうではないとわたしは思います。
享楽を得て、苦行を得て、そこからの想像力。享楽のさきを見据えた。苦行のさきを見据えたから「中道」を得たのだと思うのです。
◆なぜ苦行と享楽から離れるのか
お釈迦さまは享楽と苦行から離れた方がいい、と判断されました。それはなぜか。
苦行がすぎると逃避になってしまう。逃避がすぎると肉体からの逃避、この世からの逃避になってしまう。なにより逃避への執着がうまれる。苦行をしている自分、理想の自分への執着がうまれてしまう。それではいけない。
享楽がすぎると怠惰になってしまう。怠惰が
すぎると「楽でいい、なにもしなくていい」と生きることの無意味さ、この世の無意味さに変化してしまう。楽のみを追求する自分、楽への執着がうまれてしまう。それではいけない。
そんなことではダメだ!と思ったとしても…とらわれてしまうものです。
では、どうするか。とらわれてしまうものだと、執着を持たされてしまうものだと、わたしたちはそういう生き物なんだと、よくよく認識する。そして、ときに観察するしかないように思います。
この機会が、禅宗・臨済宗であれば、坐禅や、お仏壇のまえで手を合わせる、なのでしょう。
なぜ執着がいけないかといえば、想いをずっと抱いていても仕方がない。ずっと抱いていると、自由でいられないからです。
たとえ話があります。
◆女人を抱いて川を渡るたとえ
二人の僧が川を歩いて渡ろうとしていた。見知らぬ女性も川を渡りたいと困っていた。一人の僧が、すぐに彼女を抱いて川を渡り、女性を下ろした。助けてあげたのだ。二人の僧は先を進むが、女性を助けなかった僧が口を開いた。
「お前は僧侶として女性を抱いても良かったのか?あの女性が助けを必要としていたのは明らかだったとしても」
すると、もう一人の僧が答えた。
「たしかに俺はあの女性を抱いて川を渡った。後、彼女をそこに置いてきた。しかし、お前は、まだあの女を抱いているのか」
◆「中道」を歩む
世間のなかで、人とかかわって、社会とかかわって生きていく。世界中の人々が移動するからこそ感染症も広まる。あたらしいものが出回る。しかし、それを止めるわけにはいかない。ひとりだけで生きるわけにもいかない。
執着を持たされる機会を減らすのも大事です。
コロナ禍でひとり時間が増えています。YouTubeの陰謀動画や、TVのワイドショーにまでふりまわされませんように気をつけたいものです。
しかし、人間ふりまわされてしまう。TVをつけて政府批判して喜んでいるよりも、インターネット動画配信サービスで映画やドラマを見ている方がよいのですが…。
集まってはいけないので仕方ない、集団行動は面倒くさい、しかし「ひとりでいること」の平易さの恐ろしさを垣間見ます。
コロナ禍でも自由にいたい。「中道」がヒントになると思うのです。(副住職)