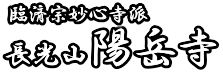山門大施餓鬼会 1日2回 5月20日(土曜)開催
◆日時 令和5年5月20日(土)
午前11時~ 午前の部(法話・法要)
午後2時~ 午後の部(法話・法要)
山門大施餓鬼会は、陽岳寺にとって長い過去をさかのぼっての有縁無縁の亡くなられた々を、みんなで感謝し、祈りを捧げる集まりです。また陽岳寺檀信徒の縁につながるご先祖様も供養しようと催される法要です。
みなさまのご参列をたまわり、コロナ対策をして開催します。お参りください。
・1日2回(午前と午後)に分散する
・先着25名ほどで各回締め切る
・どちらの回に参列希望かハガキで回答
- 参加・出席の方は「どちらの回に参列希望」「人数」「どなたに対してお塔婆を上げるか」を、電話/FAX/メール/ハガキ/振替用紙などにてお知らせください。
- 会費を払って参加するが、法要には出席しない(代理供養をご依頼の)方も、振替用紙等でお知らせください。
- 不参加の方は、ご連絡は不要です。
参加費1万円は、卒塔婆1本を含みます。
卒塔婆をさらに追加される方は、1本につき3千円を申し受けます(例:2本追加であれば、会費含み1万6千円となります)。
お塔婆に戒名を記入ご希望の場合は、戒名を明記して下さい。無記名の場合は、その家の先祖代々各霊位といたします。
【コラム】ウェルビーイング
月に2回オンライン坐禅会を行っています。坐禅と申しますと、すわって、足を組んで、姿勢を正す。姿勢だけではなく、呼吸も落ち着いていく。姿勢を調え、呼吸を調えると、こころも調う。
坐禅の説明はさまざま。先日、新潟県の学童保育で坐禅会をしてきました。小学生の子どもたちにこんな話をしました。
◆すわってください
「それでは、いまから、坐禅をしてみたいと思います。カベに沿ってすわってください」
そう言うと、立っていた子どもたちはワーッとくつを脱いですわってくれました。そこでさらに私は言いました。
「みなさん、席に着いたようですね。ありがとう。それでは、もう一度お話しますね。いいですか。『すわってください』」
子どもたちは、不思議な顔をしていました。
子どもたちは立っているところから、床に並べたクッションマットの上にすわりました。しかし、「立つ」から「すわる」に姿勢が変わっただけで、それは本当に「すわる」をすることではなかったのです。
続けてこんなお話をしました。
「みんなは小学校の教室でこんなことを思うときはありませんか?はやく給食にならないかな!校庭でドッジボールしたいな!おうちに帰ってゲームしたいな!って。そんなとき、みんなのからだは教室にいるよね。でも、頭の中は、給食でいっぱいになっていたり、校庭やおうちにいるときの自分を想像しているかもしれないね。からだは教室にいるのに、幽体離脱して心がどこかへ行っちゃったみたいに。」
「さっきは『すわってください』とお話しました。「立つ」から「すわる」になったあとに、もう一度お願いをしました。それは、からだも、頭の中も、こころも、すわるをしてほしかったからです。でもみんなキョトンとしていたね。それってつまり、本当に「すわる」をしたことがないからかもしれません。今日ははじめて、本当に「すわる」をしてみましょう」
疲れているときは「すわりたい!」とイスめがけて走るでしょう。すわって休みたいからです。しかし、自宅や職場で「よし、イスにすわるぞ!」とすわることはあまりないかもしれません。本当に「すわる」をする、についてもうすこし見てみます。
◆DOとBE
英単語のDOは「する」です。BEは「ある/いる」という意味です。
本当に「すわる」の中身とは、DOよりもBEに近いと言われます。主語が動く(DO)というよりは、世界に対する姿勢・態度(BE)といっていいのだと。そのまま、ありのままに受け止める。このBEを基本姿勢にするのは「すわる」に限りません。「食べる」「触る」…どのような行為もBEでいく。
これが禅の生き方であり、だからこそ行住座臥、なにをしていても禅の修行は楽しむことができるのだ、と円覚寺の横田南嶺老大師もおっしゃっています。
このBEを一旦やりやすいようにできるのが、立っている緊張と寝ているリラックス間の丁度いい具合「すわる」座禅なのです。
たとえば「食べる」。お腹が減ってウオオ!と食べる。イライラしてドカ食い。スマートホンで動画サイトを見ながら食い。インスタ映えするパフェと自分を写真に撮り食い。
これらはまさに食べる!のDOまっしぐらですが、その中身はインスタ映えする[用意されたおいしい]を食べているにすぎない。味や見た目ではなく、[情報]を味わっている。[食べる行為]そのものを取りに行っている。
おふくろの味を本当に味わうには、[情報=いつものおいしさの記憶]を味わうのではなく、目の前をそのままに受け止めることです。BEでいること。眼耳鼻舌身意の感覚器官が、新鮮に受け止める。
すわって脱力するのはDOだが、ひざの痛みをいたわってあげたり、眠気を感じてみたり、ぜんぜんダメだなぁ、どうしようもないなぁと諦める。DOにふりまわされず、そのままを引き受けて、そのままに味わうのがBEであると。
◆ウェルビーイング
ウェルビーイングという言葉があります。SDGsのように流行する言葉となるかもしれません。
Well-Beingウェルビーイングの直訳とは「善いあり方」「良く在ること」です。
Well-をつけると、Wellではないあり方が立ち上がってくるような気がします。
コレが幸せだ!と定義すると、コレを外れたときの不幸が襲ってきてしまう。定義することは分かりやすさにつながりますが、輪郭がハッキリしない方が助かるときもある。
たしかに、コレをしているときが幸せ!アレさえあれば私は私でいられる!ソレこそが私の肩書き!と規定することは、まわりの人に伝えやすくなります。
ただし、そもそも人間のあり方や、「わたしは**です」といった宣言には根拠がありません。だれかとだれかのおかげの中に、「わたし」がいるのですから。そんな縁起という法則の中でしか生きていけないのが人間です。
であるならば、生き方としては、世界に対しての態度としては、ただそのままに味わうことこそWell-Beingかもしれません。ただただBeingでいる。コレアレソレに振り回されない。
坐禅というと、雑念をはらって、集中することのように想像されます。たしかに、禅とはジャーナ禅定、定まっているのですが、なにに集中するのか。身体と頭の中、こころがぴたりと一枚になっていること。
では、戦争に赴いてピタリと合わさっていたら銃で人を傷つけることも禅定なのか、仏教に叶うかと言えば、そうではない。それはWell-Beingではない。DOになってしまっていないか。仏教の醍醐味のひとつは、ほほえむこと。楽しむこと、世の道理的に善くあること。
つぎの詩のように、「ほほえむ」を基本姿勢、BEでいたいものです。仏像のご尊顔の多くがほほえんでいるように。
一粒でも播くまい、ほほえめなくなる種は。
どんなに小さくても、大事に育てよう、ほほえみの芽は。
この二つさえ、絶え間なく実行してゆくならば、
人間が生まれながらに持っている、
いつでも、どこでも、なにものにも、
ほほえむ心が輝きだす。
人生で、一ばん大切なことのすべてが、
この言葉の中に含まれている。(松居桃樓『微笑む禅』)
そんな善くあることのあり方を楽しむ仲間のことを、仏教ではサンガと言います。
5月第3土曜日はおせがき、みんなでみんなのご先祖さまを供養する会です。善いあり方の集まりです。昨年のご祈祷と演芸会のように、1日2回にしました。ご都合のよい時間帯(午前/午後)で、ご参加ください。(副住職)